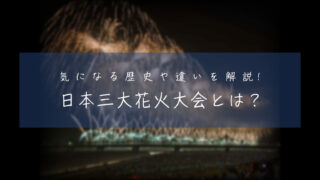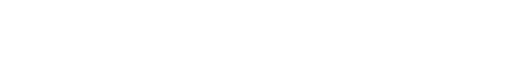長岡まつり大花火大会とは?魅力やおすすめ観覧スポットを解説
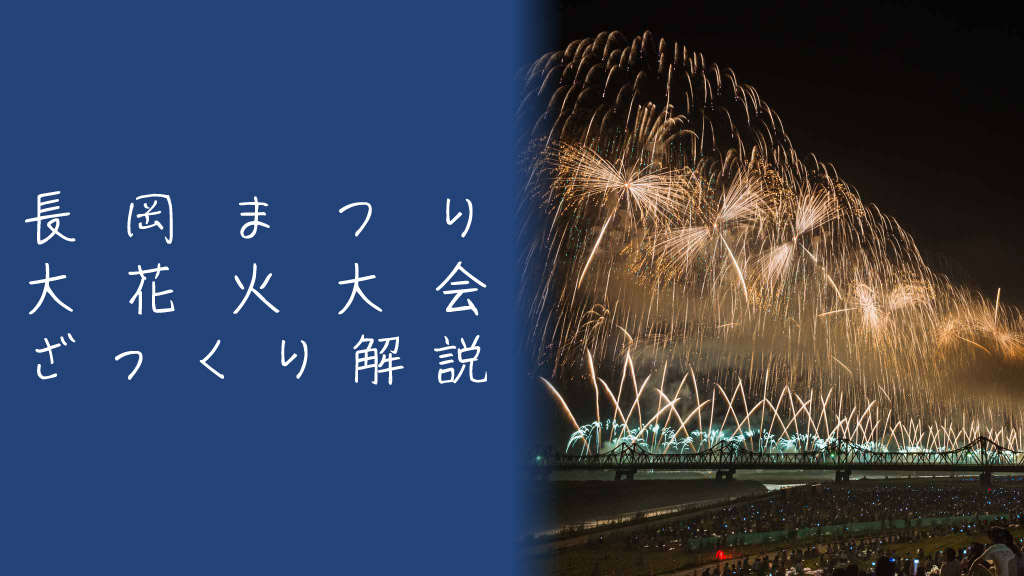
花火系散歩屋のおーわ(@mof_mof08)です。
日本各地では一年を通じてたくさんの花火が打ち上がりますが、その一つに長岡まつり大花火大会があります。
そんな長岡まつり大花火大会を観覧したいと考えている方が、おそらく僕以外に3名ぐらいはいらっしゃるんじゃないかと思います。
本記事では長岡まつり大花火大会を主に初めて観覧される方向けに、大会の概要や魅力、おすすめの観覧スポットなどについてざっくりまとめてみました。
長岡まつり大花火大会とは
長岡まつり大花火大会は新潟県長岡市で開催される花火大会で、概要は以下の通りとなります。
| 開催日程 | 2024年8月2日〜3日(※毎年8月2日〜3日) |
|---|---|
| 場所 | 信濃川河川敷 |
| 打ち上げ数 | 約20,000発(2日間合計) |
| 最大号数 | 30号玉(正三尺玉) |
| 担当煙火店 | 嘉瀬煙火工業、小千谷煙火興業、阿部煙火工業、新潟煙火工業、野村花火工業、マルゴー |
| 無料観覧席 | なし(※2022年より全席有料) |
| 有料観覧席 | あり(全席) |
| 三脚利用 | 可能 |
| Webサイト | 「長岡花火」公式ウェブサイト |
長岡まつり大花火大会の歴史は古く、1879年(明治12年)に千手町八幡様のお祭りで遊郭関係者が資金を供出しあい、350発の花火を打ち上げたのが起源とされています。
その後、1938年(昭和13年)に太平洋戦争を機に中止に追い込まれますが、1946年(昭和21年)に開催された「長岡復興祭」で花火の打ち上げが復活します。
1951年からは名称が「長岡まつり」となり、毎年8月2日〜3日の2日間(日付固定)にわたって「慰霊」「復興」「感謝」といった長岡の人々の想いを込めた花火が今日まで打ち上げ続けられています。
全国花火競技大会(大曲の花火)、土浦全国花火競技大会と共に日本三大花火大会、またぎおん柏崎まつり海の大花火大会、浅原神社秋季例大祭奉納大煙火(片貝まつり)と共に越後三大花火大会の一つに数えられています。
長岡まつり大花火大会の魅力
長岡まつり大花火大会の魅力は長岡市民の想いが込められた圧倒的スケール&芸術性の花火を堪能できる点にあります。
本大会は1日あたりおよそ40プログラムで構成されますが、その大半プログラムにおいて尺玉以上の花火が披露されます。
この時点で既に意味不明なレベルの規模ですが、それに加えて全幅約2kmから披露されるワイドスターマインや開花直径750mを誇る正三尺玉が2発以上披露されるのですから驚きです。

スポンサー協賛の花火が主体ですが、長岡空襲の慰霊と未来永劫の平和を祈念した「慰霊と平和への祈り(10号玉3発)」や自然災害(中越地震など)からの復興の祈念を目的とした「復興祈願花火フェニックス」など、長岡市ならではのプログラムも随所に盛り込まれています。


本大会の打ち上げは長岡煙火協会に属する6つ煙火店さんが担当しています。
各社とも各地の花火競技大会で優秀な成績を収めた実績があり、各プログラムにおいて芸術性に富んだ花火が堪能できます。


圧倒的なスケールと美しさだけでなく、長岡の人々の想いが乗せられているのが本大会の魅力です。
長岡まつり大花火大会の打ち上げ場所

長岡まつり大花火大会の打ち上げ場所は大きく以下の3ヶ所となります。
- 長生橋〜大手大橋(メイン)
- 大手大橋〜長岡大橋(一部プログラムのみ)
- 長生橋下流(正三尺玉のみ)
大半の花火は長生橋〜大手大橋から打ち上げられますが、以下のプログラムについては打ち上げ場所が異なります。
| 復興祈願花火フェニックス | 長生橋〜大手大橋〜長岡大橋 |
|---|---|
| 米百俵花火 | 長生橋〜大手大橋〜長岡大橋 |
| 正三尺玉 | 長生橋上流 |
基本的には長生橋〜大手大橋で打ち上げられ、プログラムによって一部異なるものがあると押さえておくとよろしいかと思います。
で、ここからは少々マニアックな話になりますが、実は長生橋〜大手大橋と大手大橋〜長岡大橋に設けられる筒の配置は地形の関係でやや変則的になっています。
先述の写真を見ていただくと何となくご理解いただけるかと思いますが、全体的にA会場側が包まれるような感じとなっています。
さらにメインの打ち上げ場所となる大手大橋〜長生橋の区間についても、少し斜めに筒が配置されます。
その関係で、有料観覧席なのにも関わらず「ここは無料観覧席か?」と思える見え方をする(その逆もしかり)観覧席がありますので、頭の片隅に置いといていただければとい思います。
長岡まつり大花火大会の観覧席
長岡まつり大花火大会では合計20種類の有料観覧席が設けられます。

いや、ちょっと多すぎて訳分からんのだが?!
そんな心の声が僕の他3名ぐらいから漏れ聞こえてきましたので、選ぶ際のポイントや注意点についてもう少し詳しく解説していきます。
観覧会場は交通手段を軸に決めるのがおすすめ
長岡まつり大花火大会の観覧席は大きくA会場(長岡駅側/右岸)とB会場(長岡インター側/左岸)に分類されますが、どちらの会場で観覧するかは交通手段を軸に決めるのがおすすめです。
表にまとめるとこんな感じ。
| 交通手段 | A会場 | B会場 |
|---|---|---|
| 公共交通機関 | ○ | △ |
| 車 | ○ | ○ |
長岡駅からメイン会場までは距離があり、A会場まで徒歩でおよそ20〜25分、B会場までおよそ45〜50分ほど要します。
さらに、A会場とB会場を結ぶ大手大橋と長生橋では花火打ち上げ時間帯の前後に大規模な交通規制が敷かれ、この間は徒歩での往来が困難になります。
B会場で観覧した後に長岡駅へ向かった場合、混雑状況によっては帰りの終電に間に合わなくなってしまうなんて可能性も…。
特に公共交通機関でアクセスされる方はA会場がおすすめです。(車でアクセスされる方はどちらの会場でもOK)
希望の観覧席で見られるとは限らない
そしてもう一つの注意点として、希望の観覧席が得られるとは限らない点です。
長岡まつり大花火大会の有料観覧席における一次販売は抽選方式となっていて、たとえ申し込んだとしても確実に入手できる保証はありません。
また、これまでは落選しても無料観覧席で見る選択肢がありましたが、全席が有料化された現在ではそういった選択ができなくなっています。
特に花火がよく見える長生橋〜大手大橋の観覧席(A会場、B会場共通)は非常に人気なため、落選する可能性が十二分にあり得るため注意が必要です。
長岡まつり大花火大会のおすすめ観覧スポット
長岡まつり大花火大会を最大限に楽しむのであれば、A会場(長岡駅側/右岸)の大手大橋〜長生橋に設けられる観覧席で見るのが最もおすすめです。
先述でも触れていますが、観覧会場は信濃川を境に2つに分かれ、さらに大手大橋と長生橋を境に5つに区分されます。
それぞれの区画での見栄えはざっくり以下の通りです。(個人的な所感を多分に含みますw)
| 区画 | A会場 | B会場 |
|---|---|---|
| 長生橋〜大手大橋 | ||
| 長生橋上流 | – | |
| 大手大橋下流 |
5つある区画のうち、大半のプログラムを最高の形で楽しめるのはA会場の大手大橋〜長生橋にある観覧席のみとなります。
以下、過去に観覧したことのあるスポットについてざっくり紹介しますので、席選びの参考にしていただければ幸いです。
ベンチ席は当たりハズレが大きい
A会場の大手大橋〜長生橋に設けられる観覧席の一つ。
長岡まつり大花火大会の観覧席の中でもベストスポットの一つに挙げられますが、河川敷堤防法面全体(直線距離およそ650m)に設けられる関係で、割り当てられる席によって花火の見え方に差異が生じます。
長生橋寄りの観覧席はスターマインと復興祈願花火フェニックスがおおむね綺麗に見える一方、正三尺玉+ナイアガラ大瀑布のバランスがやや悪い傾向にあります。



一方で大手大橋寄りの観覧席は悲惨で、プログラムの大半を占めるスターマインが無料席並の見え方をしてしまうのが辛いところ。

さらに、復興祈願花火フェニックスは大手大橋の橋脚により低い花火の一部が遮られてしまいます。

唯一、正三尺玉+ナイアガラ大瀑布が概ね綺麗な形で見られるのが救いでしょうか。

ベンチ席はおすすめの観覧席の一つですが、運ゲー要素が強い観覧席なんだと頭の片隅に置いといていただければと思います。
南エリア席(A会場)は意外と良席?!
A会場の長生橋上流に設けられる観覧席。(2019年までは無料観覧席の一つ)
ベストスポットとして挙げたA会場の大手大橋〜長生橋からは外れていますが、個人的にはそこそこの良席だと思っています。
というのも実はこの観覧席、ベストスポットからやや外れているにも関わらず、スターマインがそれなりに綺麗に見えるのです!

しかも、長岡のランドマークとして親しまれている長生橋とのコラボレーションまで拝めるのですから、お得にも程があるわけです。
さすがに復興祈願花火フェニックスはA会場の大手大橋〜長生橋の観覧席と比べて少し歪な見え方になってしまいますが、長生橋をバックに打ち上がる様子は映えLv.999です。

そしてもう一つ、この観覧席は正三尺玉の打ち上げ場所に最も近いのも特徴。

見どころであるナイアガラ大瀑布とのコラボレーションを楽しめないのは残念なところですが、五臓六腑に染み渡る正三尺玉の迫力はとにかくヤバいの一言!!
A会場の大手大橋〜長生橋を得られなかった際の第二候補として、映えるスターマインを写真や動画へ収めたい方におすすめです。
フェニックスエリア席はフェニックス花火のための席
A会場の大手大橋下流側に設けられる観覧席の一つ。
フェニックスエリア席の特徴をざっくりまとめると、とにかくプログラムによって見え方が超極端の一言に尽きます。
長岡まつり大花火大会の目玉プログラムの一つ、復興祈願花火フェニックスは概ね綺麗な形で楽しめるかつ迫力を味わえます。

しかしながら、それ以外のスターマインや正三尺玉については綺麗に見えないかつ、迫力もガクッと落ちてしまいます。

とにかくフェニックス花火を楽しみたい方にはおすすめの観覧席です。
南エリア席(B会場/あか)はスターマインが綺麗に見える
B会場の大手大橋〜長生橋に設けられる観覧席。
長岡まつり大花火大会におけるベストスポットにあたる観覧席ですが、場所選びさえ間違わなければ(詳細は後述、ここテストに出ますw)綺麗な形でスターマインを拝めます。

復興祈願花火フェニックスについても概ね綺麗な形で楽しめますが、A会場の大手大橋〜長生橋の観覧席とは対照的に包容感は得られません。

A会場の大手大橋〜長生橋の観覧席では正三尺玉+ナイアガラ大瀑布が楽しめると紹介しましたが、B会場の同区間の観覧席では残念ながら綺麗な形で拝めません。

エリア内自由席がゆえに場所取りの手間がありますが、車でアクセスされる方におすすめです。
【番外】会場外の高台からも意外と楽しめる?!

会場外にある高台からも長岡まつり大花火大会を拝むことができます。
特に復興祈願花火フェニックスは全幅が2kmと非常に広大かつ緩やかな曲線を描く形で花火筒が配置されるため、メイン会場からは少し独特な見え方をします。(先述の写真を参照)
一方で高台からであれば一直線に整った不死鳥の舞を拝めます。
花火まで距離がかなり離れているため迫力は皆無ですが、観覧チケットを入手できなかった場合は高台に出向くのもありかもしれません。
なお、会場外から観覧される場合は携帯ラジオなどを持参し、FMながおか(80.7MHz)の特番「FM三尺玉」を視聴しながら観覧すると会場の雰囲気を味わえますので参考までに。
長岡まつり大花火大会における宿泊事情とおすすめエリア
遠方から長岡まつり大花火大会へ訪れる方にとって気になる宿泊事情ですが、個人的な体感としては宿泊地の確保は少々苦労します。
長岡まつり大花火大会は長岡市の中心市街地付近で開催されるがゆえ、宿泊施設自体は会場の周辺(JR長岡駅および関越自動車道 長岡IC付近)にそれなりの数が設けられています。
しかしながら長岡まつり大花火大会は日本三大花火大会がゆえ、2日間で全国各地から花火観覧客がやってくるため、市内の宿泊施設だけでは賄いきれないのが実情です。
特に長岡市内の宿泊施設についてはかなり前から予約されている方もいらっしゃるようで、基本的に会場周辺での宿の確保は困難だと思っていただいてよろしいかと思います。
長岡市外へ範囲を広げるとそれなりの数があり、以下のエリアが候補として挙げられます。(括弧書きは公共交通機関を利用してアクセスされる方向け)
- 新潟市内(新潟駅周辺)
- 燕・三条・岩室・弥彦(燕三条駅周辺)
- 柏崎・寺泊(柏崎駅周辺)
- 上越・糸魚川(直江津駅周辺)
- 南魚沼・十日町・六日町(浦佐駅、小出駅、六日町駅周辺)
- 湯沢・苗場(越後湯沢駅周辺)
このうち新潟市内(新潟駅周辺)は宿泊施設が豊富に揃っているので、特に遠方から長岡まつり大花火大会へ初めて訪れる方はこのエリアで探すと比較的見つけやすいかなと思います。
その他のエリアについては宿泊施設がそれほど多くないかつ、どちらかといえば自家用車でアクセスされる向けでしょうか。
注意点として、おおよそどの宿泊地も需要を見越して値段が倍もしくはそれ以上に跳ね上がる傾向にあります。
特別価格やルームチャージ制を敷くところが多く、特に少人数であればあるほど宿泊費が高く付くのが非常に辛いところ。
長岡まつり大花火大会における宿泊地探しはかなり大変なため、なるべく早めに動くのが個人的におすすめです。
| 新潟市内(新潟駅周辺) | |
|---|---|
| じゃらん | 楽天トラベル |
| 燕・三条・岩室・弥彦(燕三条駅周辺) | |
| じゃらん | 楽天トラベル |
| 柏崎・寺泊・長岡・魚沼(柏崎駅、長岡駅、小千谷駅、小出駅周辺) | |
| じゃらん | 楽天トラベル |
| 南魚沼・十日町・津南(浦佐駅、六日町駅、石打駅周辺) | |
| じゃらん | 楽天トラベル |
| 湯沢・苗場(越後湯沢駅周辺) | |
| じゃらん | 楽天トラベル |
| 上越・糸魚川(直江津駅周辺) | |
| じゃらん | 楽天トラベル |
まとめ
本記事では長岡まつり大花火大会を観覧するにあたって押さえておきたい見どころや観覧席の特徴などについて紹介してまいりました。
日本三大花火大会ならびに越後三大花火大会に数えられ、「慰霊」「復興」「感謝」といった長岡市民の想いを載せて今日まで打ち上げられ続けています。
観覧席は大きくA会場(右岸/長岡駅側)とB会場(左岸/長岡IC側)に別れますが、両会場は距離があるかつ大規模な交通規制が敷かれるため、主たる交通手段に応じて選択するようにしましょう。
初めての方は長生橋〜大手大橋に設けられる観覧席(特にA会場)でご覧いただくのが最もおすすめでしょうか。
日本三大花火大会がゆえに遠方から訪れる方も非常に多いため、宿泊施設の確保には苦労する可能性がありますのでご注意を。
最後までご覧いただき、ありがとうございますm(__)m